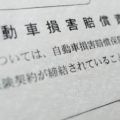交通事故で示談をする際の手続きや流れ等の注意点について


-
【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
交通事故の被害に遭った場合、被害者の方は加害者と示談交渉をする必要が生じます。
「示談」とは紛争を解決する手段の一つですが、交通事故の被害者のほとんどの方は示談の手続きについてご存じないことでしょう。
交通事故では、示談の手続きについて知らなかったり、保険会社の提案内容どおりに示談をすることで、不利益を被るケースが多いため、注意しなくてはなりません。
そこで本記事では、交通事故の被害者の方が適切に示談できるように、示談の手続きや流れ、さらには弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。
交通事故の示談とは
示談とは、当事者間の紛争を裁判外で解決することをいいます。基本的には当事者双方の譲歩によることから、民法に定められる和解の性質を有します。交通事故事件においては、まずは示談により解決が図られ、それにより話がまとまらなかった場合に裁判となる流れが一般的です。
なお、損害保険料率算出機構による2019年3月末の統計では、任意保険の加入率は74.9%となっています。そのため、被害者が実際に示談交渉を行う相手方は、多くの場合、加害者が加入する任意保険会社の担当者となります。
示談金の損害項目
交通事故における損害賠償金の算定方法は、公正で迅速な交通事故被害者救済のため、損害賠償額算定基準という形で体系化されています。これにより、主に以下の項目が定められています。
【積極損害】
- 治療関係費:病院の治療費や柔道整復師の施術費のほか、温泉療養費や将来手術費が認められる場合があります。
- 将来介護費:後遺障害を負った被害者について、職業付添人や近親者付添人が必要な場合、本人の損害として認められることがあります。
- 通院交通費:通院等のため公共交通機関やバスを利用した場合の費用が該当します。
【消極損害】
- 休業損害:交通事故により休業を余儀なくされた場合に、その減収分を損害として計上することができます。
- 逸失利益:交通事故に遭う前の収入を100%として、後遺障害を負ったことによる労働能力の喪失率をそれに乗じた上、その状態が以後何年間続くか、という算定方法により算出されます。
【慰謝料】
慰謝料は、精神的被害に対する損害賠償を指しますが、交通事故においては「死亡慰謝料」、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」という形で、それぞれ算定基準が定められています。
【物損】
「修理費」や「買替差額」等、自動車に関する費用のほか、交通事故により破損した衣類その他物品に関する費用が該当します。
示談の3つのタイミングと流れ
交通事故における示談のタイミングは、主に次の3つの時点です。以下、それぞれについて解説いたします。
1.交通事故後~治療中
1つ目のタイミングは、事故発生から数か月が経った、未だ治療継続中の時点です。特にむち打ち等他覚的所見の乏しい症状で通院している場合、被害者としてはまだまだ治療が必要だと考える段階でも、保険会社は治療費支払の打切りと併せて示談を提案してくることがあります。
示談が完了した場合、その後に交通事故に起因する症状について治療を受けたとしても、それに係る治療費を請求することはできません。そのため、保険会社による治療費支払の打切りが強行された場合でも、その時点で示談に応じることは避けるべきです。
健康保険を使用して治療を継続の上、自身が納得できるタイミングで示談交渉を開始するようにしましょう。なお、通院回数は入通院慰謝料の算定に影響するため、保険会社に先導されることなく、自身が納得できる適切な回数の通院を行う必要があります。
また、事故発生当初は物損事故として処理した上で通院を開始した場合は、可能な限り人身事故に切り替えるようにしましょう。交通事故証明書における照合記録簿の種別は、後遺障害の等級申請を行う際にある程度重要な意味を持つためです。
2.症状固定後
症状固定とは、治療効果が望めなくなり、残存症状が一進一退の状態となることです。この状態を医学的に判断することは、特にむち打ち等の目に見えない症状については実は簡単ではありません。
しかしながら、現実には、治癒に至らない症状はどこかの時点で症状固定と診断されます。これは、いつまでも治療費を支払い続けることはできないという保険会社の事情によるところが大きく、区切りとなる日が便宜的に定められるものといえます。
保険会社は、この診断をもって晴れて交通事故事件の解決を図ることができることになっています。そのため、症状固定後に後遺障害の等級申請を行う場合を除き、症状固定は示談交渉を開始するタイミングとなります。
なお、症状固定後は、保険会社からの治療費支払は受けられませんが、症状が残っている場合には、症状緩解・後遺障害等級審査の両面から、治療は継続することをお勧めします。
3.後遺障害等級認定後
症状固定と診断された場合、その旨を記載した後遺障害診断書をもって後遺障害の等級申請を行うことができます。この手続きを踏む場合、等級審査の結果(異議申立てを行う場合にはその結果)が出た後に示談交渉に進むこととなります。
示談成立と示談金の受け取り
示談は当事者双方による協議、譲歩により、その内容を決定します。そして、示談内容が決定した際は、損害賠償金の総額とその内訳等を記載した示談書(免責証書)を作成し、当事者双方がサインします。保険会社は、かかる書面の支払条件に従い、被害者に対して損害賠償金を支払います。
示談金の相場
示談金の総額は事案ごとに異なるので、相場を一概に示すことは困難です。ここでは、典型的なケースを例として、示談金の目安をご紹介します。
怪我が治癒したケース
交通事故でむち打ちになり、3か月の通院で治癒したとします。この場合の示談金の目安は以下のとおりです。
| 損害項目 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 37万8,000円 | 53万円 |
「任意保険基準」とは、任意保険会社が示談金を算出する際に用いる算定基準のことです。最低限の算定基準である自賠責基準に近い基準となっているので、示談金の提示額は低めになります。
「弁護士基準」とは、弁護士や裁判所が損害賠償金を算出する際に用いる算定基準のことです。過去の裁判例を分析して基準化されているので、正当な金額を算出することができ、任意保険基準より大幅に高額となることが多いです。
なお、怪我が治癒したケースにおける示談金としては、入通院慰謝料の他にも治療関係費、休業損害、通院交通費などを請求できます。
治療関係費は、保険会社が医療機関へ直接支払うのが通常です。休業損害は、月収30万円の人が怪我の治療のために1か月休業したとすれば、30万円程度が目安となります。通院交通費は、原則として実額が賠償されます。
後遺障害が残ったケース
交通事故でむち打ちになり、6か月の通院で症状固定の診断を受け、14級9号の後遺障害に認定されたとします。この場合の示談金の目安は以下のとおりです。
| 損害項目 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 64万2,000円 | 116万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
| 逸失利益 | 47万8,250円 | 114万5,000円 |
| 合計 | 144万0,250円 | 340万5,000円 |
逸失利益の金額は、後遺障害等級や被害者の年齢、年収によって異なります。上記の金額は、被害者が症状固定時に40歳で、事故前の年収が500万円のケースで計算したものです。
むち打ちのケースでは労働能力が失われる期間が問題となることが多く、任意保険会社は弁護士基準よりも短い期間で計算することがほとんどです。
上記の計算例では、任意保険基準で2年、弁護士基準で5年として算出しています。
なお、後遺障害が残ったケースでも、上記の損害項目の他に、治療関係費、休業損害、通院交通費を請求できます。
死亡事故のケース
死亡事故で、被害者が死亡時40歳で妻子を養っていて、事故前の年収が500万円だとすれば、示談金の目安は以下のようになります。
| 損害項目 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 死亡慰謝料 | 1,450万円 | 2,800万円 |
| 逸失利益 | 6,414万4,500円 | 6,414万4,500円 |
| 葬儀費 | 60万円 | 150万円 |
| 合計 | 7,924万4,500円 | 9,364万4,500円 |
逸失利益については、被扶養者が3人以上いる場合は、基本的に任意保険基準と弁護士基準とで同じ金額となります。しかし、被扶養者が2人以下のケースでは、任意保険基準による金額が低くなることが多いです。
保険会社は、慰謝料と比べると逸失利益をしっかり認めてくる傾向にありますが、それでも満額は提示してこないのが通常です。まして当事者相手であれば尚のことです。
以上の計算例は、あくまでも目安ですが、損害が大きくなればなるほど、任意保険基準と弁護士基準とで金額の差が大きくなることが分かるでしょう。
示談交渉にかかる期間
多くのケースについては、3か月を交渉期間のおおよその目安としていただいて良いかもしれません。お怪我がなければ、物損の話だけとなりますから、事故から3か月程度のうちに決着するケースもあります。
ただ、過失割合について折り合えないと、交渉が延々と続き、裁判せざるを得ないことになりやすいのも物損事故の特徴です。
他方、お怪我がある場合は、入通院治療を終え、収入資料等を整えて交渉を開始してから3か月程度が目安となります。例えば、3か月間通院した場合、その後に1か月程度準備期間をとって交渉を開始してから3か月程度が交渉期間の目安となります。
後遺障害の等級申請をする場合は、後遺障害診断と等級認定の期間として、さらに3~4か月間加算されます。
なお、死亡事故のケースでは、刑事手続終了後、すぐに示談交渉に入っていくケースが多くその時点から3~6か月程度が交渉期間の目安となります。
示談前にお金を受け取る方法
事故発生から示談成立までには数か月から場合によっては数年かかることもあるので、その間にお金が必要になることもあるでしょう。
そんなときは、以下の方法によって示談前にお金を受け取ることもできます。
被害者請求
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者自身が自賠責保険金の請求をすることです。
任意保険会社が支払う示談金は、自賠責保険会社が負担する部分と、任意保険会社が上乗せする部分の二重構造になっています。
示談成立後に任意保険会社が全額を一括して被害者に支払い、その後、自賠責保険会社が負担する部分を回収するのが一般的な流れです。
しかし、自賠責保険会社が負担する部分は、示談前でも被害者が直接請求して受け取ることが可能です。ただし、被害者請求によって受け取れる保険金には、次にように限度額があります。
| 損害の種類 | 限度額(被害者1名につき) |
|---|---|
| 傷害による損害 | 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 4,000万円 ※後遺障害等級によって異なる。14級の場合は75万円。 |
| 死亡による損害 | 3,000万円 |
仮渡金の請求
自賠責保険には、仮渡金という制度もあります。被害者からの請求により、損害の程度に応じて賠償金の一部が仮に支払われるという制度です。 仮渡金の請求によって受け取れる金額は、死亡事故では被害者1名につき290万円、怪我をした事故では負傷の程度に応じて5~40万円で一定額が定められています。 仮渡金を受け取った場合、示談交渉では仮渡金の金額が示談金から差し引かれます。
内払い金の請求
内払い金とは、示談前に任意保険会社から示談金の一部を支払ってもらう仕組みのことです。制度化されているわけではないので、内払い金を受け取るためには任意保険会社との交渉が必要です。
ただ、休業損害や通院交通費については、1か月ごとの支払いに応じてもらえる可能性が十分にあります。慰謝料の内払いに応じてもらえるケースもありますが、治療期間が長引くなどのケースに限られるようです。
示談交渉でもめやすいポイント
示談交渉では、様々な争点でもめることがあります。特にもめやすいポイントは、以下の3点です。
過失割合
保険会社が被害者に不利な過失割合を主張することは、よくあります。例えば、被害者が無過失の事故でも保険会社が「被害者にも2割の過失がある」などというケースは多いです。
この場合、保険会社の言うことを鵜呑みにして示談すると、過失相殺によって示談金が20%減額されてしまうので注意が必要です。
保険会社にとっての顧客は加害者なので、保険会社は加害者の言い分に従って過失割合を主張する傾向にあります。そのため、過失割合でもめたときは、事故の発生状況を客観的に証明することが重要です。
ドライブレコーダーや現場周辺の防犯カメラの映像に事故の発生状況が記録されていれば、強力な証拠になります。このような映像がない場合は、警察が作成した実況見分調書などの刑事記録を取り寄せるのが一般的です。
後遺障害等級
保険会社は損害保険料率算出機構による後遺障害の認定結果に従って、示談金を計算することがほとんどです。しかし、被害者が認定結果に納得できないことも多いものです。
特に、むち打ちで痛みやしびれが残っているのに後遺障害に認定されないケースが、多々あります。このような場合には、損害保険料率算出機構に対して異議申し立てを行い、適正な後遺障害等級への認定を獲得することが大切です。
他覚的所見のないむち打ちでも、事故直後から痛みやしびれなど特定の症状が一貫して表れていたことを証明できれば、14級9号の後遺障害に認定される可能性があります。
そのためには、治療を受けた病院からカルテやレントゲン写真などを取り寄せるほか、追加でMRIや神経学的検査を受けたり、医師の意見書や被害者自身の陳述書などの証拠を準備するのが有効です。
慰謝料額
任意保険基準と弁護士基準では、慰謝料額に大きな開きがでます。ただ、被害者自身が弁護士基準で慰謝料を請求しても、保険会社が応じることはほとんどありません。
そのため、被害者が泣き寝入りしない限りは、慰謝料額でもめることになります。
弁護士基準で計算した慰謝料を受け取るためには、基本的には裁判をするか、弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。
被害者が弁護士に依頼した場合、保険会社も裁判を恐れて示談に応じることが少なくありません。そのため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故の示談における注意点
実際に示談交渉を行う際にはいくつかの注意点がありますので、以下でそれぞれ解説いたします。
安易に示談を受けてはいけない
前述のとおり、示談のタイミングは主に3つ想定されますが、保険会社としてはできる限り早期に解決を図り、支払金額を低額に抑えたいと考えています。そのため、ときには積極的に示談を持ち掛けてきます。
被害者としては、保険会社のペースに飲まれることなく、必要な治療や等級申請の手続きを経たところで示談交渉を開始しなければなりません。
示談に合意すればやり直しはできない
示談書には、被害者が「今後裁判上、裁判外を問わず、一切の異議申立てや請求を行わない」旨を記載することになります。これにより、被害者は示談書記載の条件以上の請求権を放棄することとなるため、示談が完了すると、以降再度の協議や追加請求を行うことは基本的にできなくなります。
なお、昭和43年3月15日の最高裁判決では、「交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、少額の賠償金をもって示談がされた場合、右示談によって被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであって、その当時予想できなかった後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。」とされており、示談後においても例外的に追加請求できる場合があることを謳っています。
弁護士基準により示談金を請求すること
交通事故における損害賠償金の算定基準は、最低額を定める自賠責基準、自賠責基準に近似する任意保険基準、そして弁護士が交渉に用いる裁判基準が存在します。
保険会社が提示してくる賠償金額案は、基本的に任意保険基準によって算定されています。被害者としては、保険会社の提示をそのまま受け入れるのではなく、裁判基準により算出される金額をしっかりと主張するようにしましょう。
示談をしないとどうなる
「加害者が示談交渉に応じない」、「保険会社の対応が悪く話したくない」等の理由により、示談交渉を放置してしまう被害者の方がいらっしゃいます。お気持ちはよくわかりますが、これにより、大きな損失を被ってしまう場合があります。
交通事故における示談交渉は、損害賠償金の支払を受けるために行うものです。したがって、法的な性質としては「不法行為による損害賠償請求」となります。そして、かかる請求権には消滅時効が定められています。
不法行為による損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時」から進行し、「人の生命又は身体を害する不法行為」については5年間、それ以外では3年間行使しないと消滅してしまいます。そのため、具体的には次の期間が経過することで請求権は消滅します。
- 物損事故:事故日の翌日から3年間
- 傷害部分:治癒した日又は症状固定日の翌日から5年間。ただし、事故日を基準とする説も存在します。
- 後遺障害:症状固定日の翌日から5年間
- 死亡事故:死亡日の翌日から5年間
なお、後遺障害の等級申請を含む自賠責保険への請求権については、自動車損害賠償保障法にて別途消滅時効が定められているため注意が必要です。
各時効が心配な場合は、裁判上の請求や時効中断申請等の措置をとる必要があります。
自分で示談交渉をする場合のリスク
保険会社との示談交渉は自分でもできますが、以下のようなリスクがあることに注意が必要です。
適正な示談金額が分からない
適正な示談金額とは、弁護士基準で計算した示談金額のことです。保険会社が提示する示談金額は適正な金額よりも大幅に低いことが多いですが、被害者自身はどれくらいの金額が適正なのかが分からないでしょう。
その他にも、過失割合や後遺障害の認定結果が適正であるかどうかの確認も難しいと考えられます。
保険会社からの提示を鵜呑みにして示談に応じてしまうと、示談金で大きな損をする可能性が高いです。
手間とストレスがかかる
示談交渉をするには、保険会社の担当者と何度も連絡を取り合わなければなりません。それだけでも手間とストレスがかかります。
適正な示談金額を請求するためには、交通事故の損害賠償に関する専門的なことを調べ、適切な計算方法で示談金額を算出し、様々な証拠を集めなければなりません。
自分ですべてのことに対応するとなると大きな手間とストレスがかかり、治療や仕事、家事などに専念することは難しくなることもあるでしょう。
担当者に言いくるめられるおそれがある
保険会社の担当者は、示談交渉のプロです。専門的な知識や経験、交渉力の面で、被害者との差は歴然としています。そのため、自分で保険会社と対等に交渉することは、そもそも困難なのです。
たとえ被害者が正当な主張をしても、担当者は「それなら裁判をしてください」と言うだけで、譲歩などはしないことがほとんどです。
被害者としては、裁判をしたいと考えてもどうすればよいのかが分からず、途方に暮れてしまうでしょう。なす術がないまま担当者に言いくるめられ、不当に低い金額で示談をしているケースは多々あります。
交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット
交通事故の示談交渉は、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士の力を借りることで、以下のメリットが得られます。
手続きを全面的に任せられる
弁護士は、被害者の代理人として保険会社と交渉します。被害者は自分で保険会社とやりとりする必要がなくなります。
証拠の収集も弁護士がサポートしてくれますし、裁判が必要になった場合も、複雑な手続きはすべて弁護士が代行してくれます。
このように、示談交渉の手続きはすべて弁護士に任せられるので、被害者は手間やストレスから解放されます。
示談金を早めに受け取れる
弁護士に示談交渉を依頼すると、示談金を早めに受け取ることも可能となります。弁護士は示談交渉に慣れていて、主張・立証すべきポイントや落とし所も熟知しているので、交渉をスムーズに進めてくれるからです。
保険会社と意見が対立する場合、被害者が自分で交渉すると平行線が続き、交渉が長引くことが多いです。しかし、保険会社も弁護士が介入すると裁判を恐れて態度を軟化させるので、交渉期間が短縮されます。
交通事故に遭って苦しい思いをしている中で、示談金を早めに受け取れることは大きなメリットのひとつでしょう。
示談金の大幅アップが期待できる
弁護士は、示談金を弁護士基準で計算して保険会社に請求します。保険会社も、弁護士との交渉では弁護士基準による金額で示談に応じることが少なくありません。
これだけでも、示談金の大幅アップが期待できます。その他にも、弁護士のサポートを受ければ、過失割合や後遺障害等級などの争点で正しく主張・立証できるので、適正な解決を図りやすくなります。
その結果、保険会社の提示額よりも大幅にアップした示談金を受け取れる可能性が高まります。
まとめ
交通事故は、訴訟による解決は稀で、ほとんどのケースが示談によって解決をすることになります。そのため、被害者の方は示談手続きについて理解するとともに、適切な手続きをおこない解決することが必要です。
しかし、保険や法律などの知識を持たない一般の方にとって、百戦錬磨のプロである保険会社との交渉は簡単ではありません。
もし、事故に遭われた場合、交通事故に詳しい弁護士に依頼して示談交渉を任せることをおすすめします。
弁護士法人オールイズワンは、交通事故事件の解決を主業務として長年取り組んでまいりました。その経験から、示談交渉に関して適切なアドバイスやサポートを提供することが可能です。
交通事故における示談に係る諸問題でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。