交通事故の死亡保険金に税金はかかる?課税されるケースとされないケースを解説
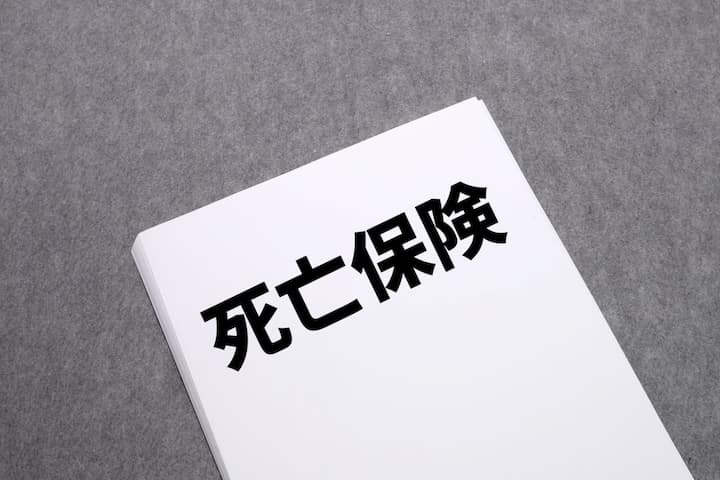
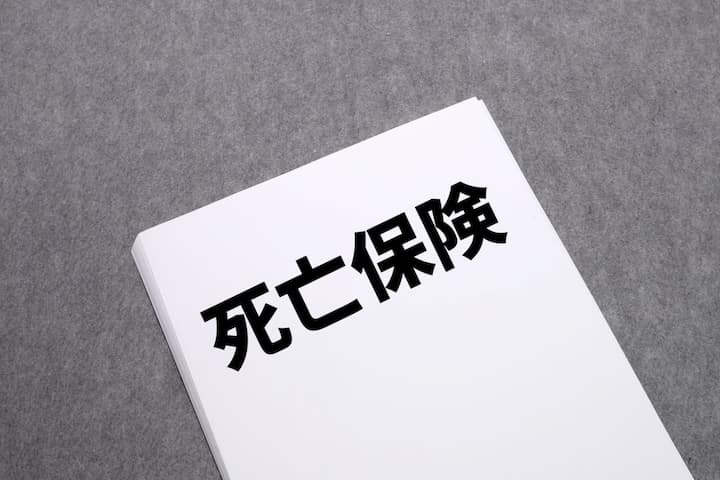
死亡事故では、加害者側に請求できる損害賠償金が高額になることが多いです。自動車保険の他にも、生命保険などで保険金を受け取ることもあります。
これらの死亡保険金に、多額の税金がかかるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、交通事故の死亡保険金に税金はかかるのか、かかる場合にはどのような税金がかかるのかについて解説します。
「思ったほど手元にお金が残らない」といった事態を回避するためにも、最後までお読みいただくことをおすすめします。
死亡保険金の損害賠償金は原則として非課税
交通事故の死亡保険金のうち、損害賠償金としての性格を有するものには、原則として税金はかかりません。
損害賠償金は事故によって被害者側に生じたマイナス(損害)を補填するために支払われるものであって、被害者側に利益をもたらすものではないからです。
損害賠償金に税金がかかるとすると、被害者側は十分な補償を受けられなくなってしまうため、加害者が本来負担すべき金額については原則として非課税とされているのです。
交通事故で加害者側の自動車保険会社が支払う死亡保険金は、損害賠償金としての性格を有するものですので、加害者が本来負担すべき金額を超えない限り、税金がかかることはありません。
交通事故の死亡保険金に税金がかかるケース
交通事故を原因として支払われる死亡保険金であっても、以下のものは損害賠償金としての性格を有しないため、税金がかかります。
生命保険や医療保険の死亡保険金を受け取った場合
生命保険の契約に基づき支払われる死亡保険金は、それまでに支払った保険金の対価として支払われるものです。損害の補填を目的としたものではないので、損害賠償金とは性格が異なります。
死亡保障付きの医療保険から支払われる死亡保険金も、同様です。
したがって、生命保険や医療保険の死亡保険金を受け取った場合は、税金がかかることがあります。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険など自分の保険を使った場合
自動車保険のうち、人身傷害保険や搭乗者傷害保険は、契約者やその家族など被害者側の損害を補填するための保険です。
交通事故で被害者が死亡した場合には、被害者本人または遺族が契約していた保険を使って、人身傷害保険や搭乗者傷害保険で死亡保険金を受け取ることもできます。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の主な違いは、人身傷害保険では実際の損害額が補償される(契約内容によっては限度額もある)のに対して、搭乗者傷害保険では契約時に定めた一定額が補償されることです。
人身傷害保険でも搭乗者傷害保険でも、被害者側の過失割合を問わず、満額が補償されます。しかし、被害者側の過失割合に相当する部分は、本来加害者が支払うべきものとはいえません。
したがって、死亡事故で被害者にも過失があった場合には、人身傷害保険や搭乗者傷害保険で支払われる死亡保険金のうち、被害者側の過失割合に相当する部分について税金がかかることがあります。
例えば、被害者に3割の過失があった場合には、死亡保険金のうち3割に相当する部分が課税対象となるのです。
相場より著しく高額の賠償金を受け取った場合
交通事故の損害賠償金には、過去の裁判例などから導かれる相場があります。
相場より著しく高額の賠償金を受け取った場合は、慰謝料などを増額すべき特段の事情がない限り、相場を超える部分は本来加害者が支払うべきものとはいえません。
したがって、相場を超える部分には税金がかかる可能性があります。
保険会社から相場を著しく超えるような金額の保険金が支払われることは、あまり考えられませんが、相場を超えた部分は課税対象となるということは知っておいた方がよいでしょう。
死亡保険金にかかる税金の種類
死亡保険金が課税対象となる場合は、以下のように被保険者(被害者)、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、課せられる税金の種類が異なります。
| 被保険者 (被害者) |
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
それぞれのケースについて、具体的に解説していきます。
所得税がかかるケース
保険料の負担者と保険金受取人が同じ人であれば、所得税の課税対象となります。
例えば、子ども(被保険者)が交通事故で死亡したケースで、父親が保険料を支払っていた保険から、父親を受取人とする死亡保険金が支払われた場合などが、所得税の課税対象に該当します。
なお、死亡保険金を一時金で受け取った場合には一時所得となり、年金で受け取った場合には雑所得となるため、納税額の計算方法はそれぞれ異なります。
相続税がかかるケース
被保険者(被害者)と保険料の負担者が同じ人であれば、相続税の課税対象となります。
例えば、夫(被保険者)が交通事故で死亡したケースで、夫自身が保険料を支払っていた保険から、妻を受取人とする死亡保険金が支払われた場合などが、相続税の課税対象に該当します。
死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税を計算する際には相続財産とみなされるのです。
ただし、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、相続税がかかるのは、この枠を超えた部分のみです。
なお、死亡保険金を年金で受け取る場合には、まず年金受給権に相続税がかかり、追って毎年支払いを受ける年金に所得税がかかります。
贈与税がかかるケース
被保険者(被害者)、保険料の負担者、保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税の課税対象となります。
例えば、母親(被保険者)が交通事故で死亡したケースで、父親が保険料を支払っていた保険から、子どもを受取人とする死亡保険金が支払われた場合などが、贈与税の課税対象に該当します。
この場合、保険金受取人は第三者が支払った保険料の対価を受け取ることになるため、贈与に該当するのです。
ただし、贈与税は年間110万円まで非課税とされているため、贈与税がかかるのは110万円を超える部分のみです。
なお、死亡保険金を年金で受け取る場合には、まず年金受給権に贈与税がかかり、追って毎年支払いを受ける年金に所得税がかかります。
死亡保険金にかかる税金を納めないとどうなる?
死亡保険金に税金がかかる場合は、自分で納税額を計算し、以下の期限までに申告しなければなりません。
- ・所得税…翌年2月16日から3月15日まで
- ・相続税…相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- ・贈与税…翌年2月1日から3月15日まで
所定の期限までに申告・納税をしなかった場合には、延滞税や延滞金がかかり、場合によっては加算金(過少申告加算金、不申告加算金、重加算金)がかかることもあるため、納税額が増大してしまいます。
督促を受けても滞納を続けると、滞納処分として財産を差し押さえられたり、その財産を換金(公売)されたりすることもあるので注意が必要です。
滞納額が大きく、悪質な場合には、脱税として刑事罰の対象となることもあるので、税金がかかる場合には必ず申告と納税を行う必要があります。
交通事故の死亡保険金について弁護士に相談するメリット
交通事故の死亡保険金で損をしないためには、弁護士に相談してみることをおすすめします。交通事故に強い弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットが期待できます。
税金がかかるか判断してもらえる
死亡事故の損害賠償請求を弁護士に相談すれば、提携している税理士を紹介してもらえたり、依頼した弁護士と税理士が連携して税金の問題に対応してくれます。
具体的な状況に応じて税金がかかるかを判断してもらえるので、うっかり申告せず、延滞税や延滞金を課せられるといった事態を回避することが可能です。
なお、弁護士は税金に詳しいとは限りません。一般的な無料相談などでは税金に関するアドバイスは受けられず、基本的には別途、税理士に相談しなければならないことにご注意ください。
確定申告など手続きに関するアドバイスが受けられる
死亡保険金に税金がかかるときは、確定申告など税金の申告に関する手続きについて、税理士からアドバイスを受けるのはおすすめです。
相談・依頼した弁護士から信頼できる税理士を紹介してもらえた場合には、申告手続きを依頼するのもよいでしょう。自分で別途、税理士を探して相談する手間が省けます。
税金の問題は信頼できる税理士に任せることで、交通事故の損害賠償請求の問題に集中できるようになります。
保険会社とのやりとりを任せられる
交通事故の損害賠償請求については、弁護士に依頼すると、保険会社とのやりとりを一任することができます。
大切な方を事故で亡くした心痛のさなか、弁護士が代理人として示談交渉をしてくれるので、心強い味方となるでしょう。
保険金の増額が期待できる
保険会社との示談交渉を弁護士に任せることで、死亡保険金の増額も期待できます。
なぜなら、死亡慰謝料や逸失利益、葬儀関係費用などについて、弁護士は「弁護士基準」(裁判所基準ともいいます)と呼ばれる算定基準を用いて賠償金額を計算し、請求・交渉してくれるからです。
慰謝料をはじめとする交通事故の損害賠償金には、次の3種類の算定基準があります。
- ・自賠責保険基準…自賠責保険金を算定する際に採用される基準
- ・任意保険基準…任意保険金を算定する際に採用される基準
- ・弁護士基準…過去の裁判例に基づき適正な賠償金の額を基準化したもの
損害賠償金の額は自賠責保険基準が最も低く、弁護士基準が最も高くなるケースが多いです。死亡事故では、弁護士基準による金額は他の2つの基準による金額よりも大幅に高額となるケースがほとんどです。
ただし、被害者側の遺族が自分で示談交渉をすると、通常は保険会社から任意保険基準による示談案を押し付けられてしまいます。弁護士基準による死亡保険金を獲得するためには、弁護士によるサポートが重要となります。
また、加害者が契約している保険会社から支払われる死亡保険金には、過失相殺が適用されます。保険会社は加害者に有利な過失割合を主張することが多いですが、被害者本人は亡くなっているため、反論が難しいことも少なくありません。
しかし、弁護士は実況見分調書や事故現場の写真などをはじめとして、客観的な証拠をできる限り収集し、過失割合を適正に判断して保険会社と交渉してくれます。そのため、不当な過失相殺で死亡保険金が減額されるといった事態の防止にもつながります。
結論として、交通事故に強い弁護士のサポートを受けることにより、自分で示談交渉をする場合よりも、高額の死亡保険金を受け取れる可能性が高まるといえます。
まとめ
死亡保険金のうち、損害賠償金としての性格を有するものは原則として非課税です。
加害者側の対人賠償保険や対物賠償保険を使って受け取る保険金には、税金はかからないと考えて差し支えありません。
しかし、人身傷害保険、搭乗者傷害保険を使った場合や、生命保険、医療保険(死亡保障付き)で死亡保険金を受け取る場合には、税金がかかることもあるので注意が必要です。
税金がかからない死亡保険金についても、適切な金額を獲得するためには弁護士によるサポートが重要な役割を果たします。
大切な方が死亡事故に遭われたら、まずは、交通事故に強い弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。
弁護士法人オールイズワンは、死亡事故に多くの経験と実績があります。税金の問題についても税理士と連携して対応することが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。











